
エンディングノートの必要性について解説!
人生100年時代と言われる現代、医療の進歩や生活水準の向上により、多くの方が長生きできるようになりました。しかし、長寿が当たり前になった一方で、「いつかは終わりがやってくる」ことにも改めて目を向ける必要があります。シニア世代の方だけでなく、若い世代の方でも突然の病気や事故は起こり得ます。そうしたとき、自分の想いや希望、連絡してもらいたい人などを事前に整理しておく手段として注目されているのが「エンディングノート」です。
エンディングノートとは、自分の最期に関する希望や大切な情報を残すためのノートのことです。葬儀や相続などの手続きだけでなく、医療や介護の方針、デジタル遺品の扱いなど多岐にわたる内容を記しておくことで、「自分の想いを正しく伝えたい」「家族や周囲の人々に迷惑をかけたくない」という不安や悩みを解消する一助となります。
本記事では、エンディングノートの基本的な概要から書き方のコツ、活用のポイントや注意点までを網羅的にご紹介します。終活の一環として、あるいは自分や家族の安心のために、エンディングノートの存在意義をぜひご一読いただき、ご自身なりの活用法を見つけていただければ幸いです。
エンディングノートとは

エンディングノートの定義と役割
エンディングノートは、自分が亡くなったり意思表示が難しくなったりしたときに備えて、家族や親しい人、あるいは信頼できる第三者に向けて情報や希望を伝えるためのノートです。具体的には、下記のような情報をまとめることが一般的です。
- 本人情報: 氏名、生年月日、住所、本籍地など
- 家族・親族情報: 続柄や連絡先、親しい友人の連絡先
- 資産情報: 銀行口座、保険、証券、年金、クレジットカード、負債の有無など
- 医療・介護に関する希望: 延命措置や介護施設選択、訪問介護に関する希望など
- 葬儀やお墓の希望: 葬儀のスタイル、宗教上の儀式、遺影の写真、お墓や散骨の希望など
- 遺品整理・相続に関する希望: 相続に対する考え方、形見分けの希望、遺品の取り扱いなど
- デジタル遺品に関する情報: SNSアカウント、ブログ、メールアドレス、パソコンやスマホのパスワードなど
- ペットの世話や財産: 飼っている動物がいる場合の引き取り先や費用の管理方法
- メッセージ・想い: 家族への感謝や友人へのお礼など、自由に書き残しておきたいこと
こうした情報を「一括して」まとめておくことで、万一の際に家族が混乱せずに手続きを進められたり、本人の希望を汲んだ対応ができたりするのが大きなメリットです。また、エンディングノートを通じて自分の生き方を振り返る機会にもなるため、単なる書類というだけでなく、「自分らしい最期」を考える手掛かりにもなります。
遺言書との違い
「エンディングノート」とよく混同されるものに「遺言書」があります。しかし、両者の性質は大きく異なります。遺言書は法的拘束力をもつ文書であり、財産分与や相続人の指定などを法的に有効な形で残すためのものです。一方、エンディングノートには法的拘束力はなく、あくまで本人の希望や情報を残すための“メモ”のような位置付けです。
- 遺言書
- 法的拘束力がある
- 主に財産分与・相続にかかわる事項
- 作成には法律上の要件を満たす必要がある(自筆証書遺言、公正証書遺言など)
- エンディングノート
- 法的拘束力はない
- 希望・気持ちを伝える、各種情報を整理する目的
- 書き方や形式に制限はなく、自由度が高い
遺言書は「自分の財産をどう扱ってほしいか」を正式に示すための手段であり、エンディングノートは「自分の希望や想いを伝えておきたい」「様々な情報を残しておきたい」という気持ちをかたちにする手段だと言えます。両者は役割が異なるため、「財産分与などの法的効力が必要な部分は遺言書で、その他の想いや情報はエンディングノートで」というように、うまく使い分けることが望ましいでしょう。
エンディングノートを書くメリット

1. 家族や周囲の負担を軽減できる
人が亡くなったあとに最初に発生するのが「葬儀の準備や段取り」です。どの葬儀社に頼むか、どんなスタイルの葬儀を希望していたか、宗教はどうするか、誰に連絡をするべきか……。これらを生前のうちにある程度まとめておくだけで、残された家族の精神的・時間的負担は大幅に減ります。また、財産の所在や口座情報なども整理しておくことで、相続手続きがスムーズに進みやすくなります。
2. 本人の想いを正しく伝えられる
「本当はこうしてほしかったのに、家族は知らなかったから違う形になってしまった」という状況が起こると、本人の希望が叶わないばかりか、残された側も後悔やトラブルの原因になる場合があります。エンディングノートを活用することで、自分の気持ちや希望を先に伝えられるため、最期を自分らしく迎えるうえで大きな安心感が得られます。
3. 自分自身の人生を振り返る機会になる
エンディングノートに書くべき情報を整理していると、これまでの自分の人生の歩みや財産、交友関係などを再確認することになります。「こんなに多くの人と出会ってきた」「こんな財産をつくってきた」「これはもう必要ないかもしれない」など、改めて棚卸しを行うことで、今後の生活の方向性を見直すきっかけになるでしょう。
4. もしもの際に医療や介護の意向を伝えられる
介護や医療について、本人がどの程度の治療や延命を望むかは非常に重要な問題です。しかし、その意思表示が必要になるのは、本来は本人が話せるうちに決めておくべきもの。万一、事故や病気などで意思表示ができなくなったとき、周囲は本人の本心がわからずに悩んでしまいます。エンディングノートに医療・介護に関する希望を書いておくことで、万が一の際も自分の意向を伝えられる可能性が高まります。
エンディングノートに書くべき項目と書き方
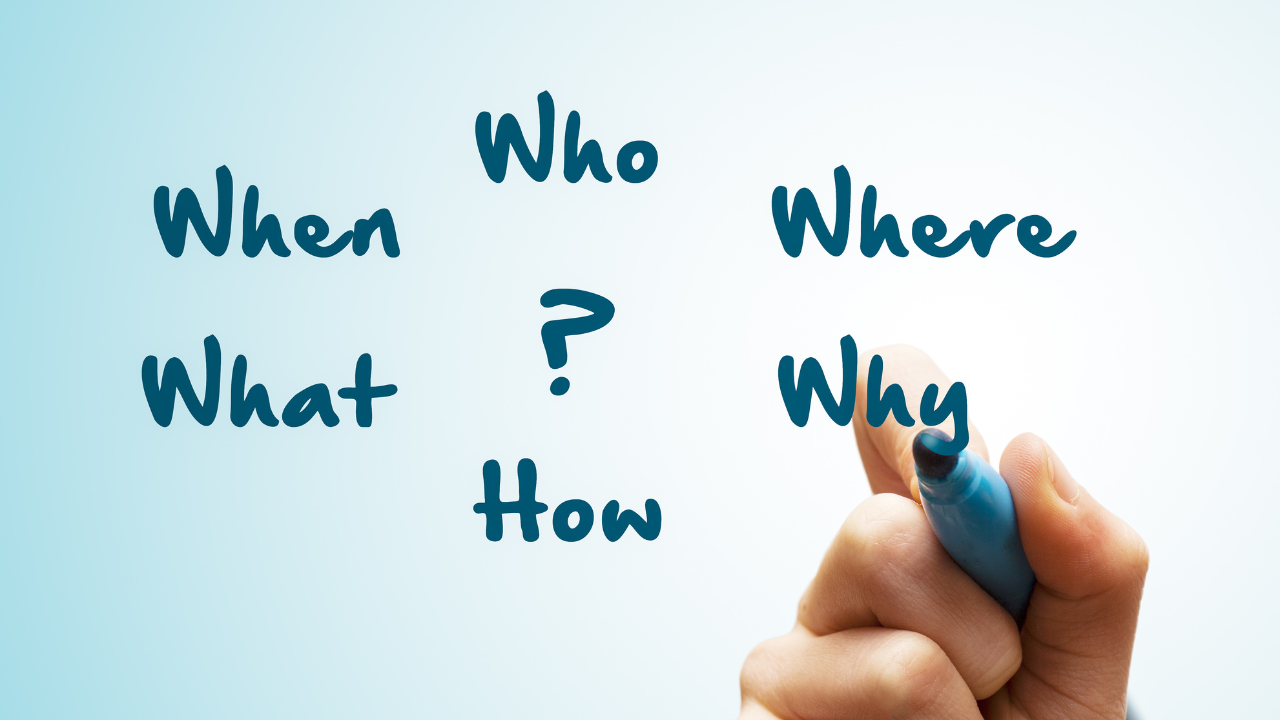
エンディングノートに書いておくと役立つ情報は多岐にわたりますが、ここでは主な項目と書き方のポイントを詳しく解説します。実際のノートは市販のテンプレートを利用したり、自分なりにカスタマイズしたりと、書く人の目的や状況に応じて自由に構成して構いません。
1. 基本情報(プロフィール)
- 氏名・生年月日・本籍地・現住所
- 公的な手続きを進める際に必ず必要になる情報です。誤字脱字がないよう正確に記入しましょう。
- 家族構成・連絡先
- 緊急連絡先(親戚、友人、知人など)も合わせて記載しておくと、本人が万一の時にも連絡漏れを防ぎやすくなります。
2. 医療・介護について
- 延命措置の希望
- どの程度の治療や延命を望むのかを明確に記しておくと、家族が迷わなくて済みます。
- かかりつけ医・よく利用する医療機関
- 健康診断や治療歴など、医療記録に関する書類や連絡先もまとめておくと便利です。
- 介護サービス利用の希望
- 在宅介護や施設介護など、どのような介護スタイルを希望するかを具体的に書いておきましょう。
3. 葬儀・お墓について
- 葬儀のスタイル
- 宗教や宗派、規模や式場、または直葬を希望するかなど。
- 葬儀社の候補
- 信頼できる葬儀社やお世話になったところがある場合には連絡先を記しておくと安心です。
- お墓の場所や埋葬方法
- 先祖代々のお墓がある場合は場所や管理方法も書いておきましょう。また、散骨や樹木葬を希望する場合は具体的な希望を詳しく記入します。
- 遺影の写真
- 本人が気に入った写真があれば、指定しておくと家族にとっても助かります。
4. 財産・資産情報
- 銀行口座や証券口座、クレジットカード
- 口座の所在、口座番号、支店名、暗証番号(暗証番号は取り扱いに注意)をまとめておくと、相続人が手続きをスムーズに進められます。
- 保険、年金、積立
- 保険証券の場所や証券番号、契約内容などを簡単にわかる形にしておくと便利です。
- 不動産
- 土地や建物の所在地、登記情報など。
- 負債やローンの情報
- 借入先や残債額、返済予定などがわかると、残された家族が後から不安にならずに済みます。
5. デジタル遺品
- メールアドレスやSNS、ブログなどのアカウント情報
- ID・パスワードの管理についてはセキュリティ上のリスクもあるため、取り扱い方には注意が必要です。暗号化して別の場所に保管し、ノートに保管場所だけを記入するなどの工夫を行いましょう。
- スマホやパソコンのロック解除
- ロック解除の方法がわからず、残された家族が困ってしまうケースも増えています。指紋認証や顔認証の場合は対応が難しい場合もあるため、PINコードやパスワードをどこに記録するか検討しておきましょう。
- サブスクリプションサービスや有料アプリの契約情報
- 月額課金サービスをどこで契約しているか、いつまで支払う必要があるかも重要です。不要な出費を続けないようにするためにも、リスト化しておくとよいでしょう。
6. ペットの世話や費用
- 飼っているペットの種類・名前・かかりつけの動物病院
- ペットは飼い主がいなくなると引き取り手がないまま苦境に立たされるケースもあります。引き取りを頼める人がいる場合は、その連絡先も記入します。
- 飼育費用や医療費の管理方法
- ペット保険に入っている場合はその情報を、入っていない場合は月々の飼育費の概算をメモしておくと、引き取り手がスムーズに対応できます。
7. メッセージや思い出
- 家族や友人への感謝や伝えたいこと
- 日頃は恥ずかしくて言えない言葉や、お世話になった方へのお礼、感謝などを書き残しておくと、残された人にとって大切な形見となります。
- 写真やアルバムの場所、思い出の品
- どこに保管しているのか、処分してほしくないものは何かなどを具体的に記しておくと、遺品整理の際に役立ちます。
エンディングノートの書き方とコツ

- 一度にすべて完璧に書こうとしない
エンディングノートは、一回書き上げたら終わりではなく、定期的に見直しながら更新していくものです。初めから100%完璧を目指すと疲れてしまうので、最初は大まかな情報から書き始め、徐々に細部を詰めるようにしましょう。 - 形式にこだわりすぎない
市販のエンディングノートを使うのも便利ですが、手書きのノートやパソコンで自作したドキュメントでも問題ありません。自分が書きやすく、見直しやすい形で作成しましょう。ただし、パソコンで作った場合は、パスワード管理などのセキュリティには留意が必要です。 - 大切な情報は安全な場所に保管し、家族に伝えておく
エンディングノートの存在を誰にも知らせないまま厳重に隠しておくと、いざという時に誰も見つけられない可能性があります。ある程度信頼できる家族や親しい友人には「エンディングノートを用意している」という事実と、保管場所を伝えておくことが大切です。 - 定期的に見直す
人生は常に変化していきます。結婚や離婚、出産、転職、引っ越しなどのライフイベントのたびに、ノートの内容も定期的にアップデートするように心がけましょう。 - 法的効力のある遺言書と合わせて利用する
相続や財産分与などに関しては、エンディングノートだけでは法的拘束力がありません。財産をめぐるトラブルを防ぐためにも、必要に応じて遺言書の作成を検討し、その概要をエンディングノートにも記載しておくと良いでしょう。
エンディングノートを活用するときの注意点

- 情報漏洩に気をつける
口座情報やパスワードなど、個人情報の流出は大きなリスクを伴います。特にデジタルデータで保存する場合はパスワードを分割管理するなどの対策を行いましょう。紙のノートであっても、保管場所を厳重にするか、必要に応じて鍵付きの金庫に保管するなどの工夫が必要です。 - 書きっぱなしにしない
「書いたから安心」と放置してしまうと、数年後には情報が古くなってしまうかもしれません。特に資産や口座情報、連絡先などは変更が生じやすいため、最低でも年に一度くらいは内容を確認することをおすすめします。 - 家族とのコミュニケーションを大切にする
エンディングノートはあくまで「書き手の希望」をまとめたものですが、それを受け取る側の家族や友人などにも気持ちがあります。生前のうちに「こういう考えがあって書いている」ということを話し合っておくと、万が一の際にスムーズに対応してもらえるでしょう。 - 法的な誤解を避ける
エンディングノートは法的拘束力がありません。相続トラブルを避けるためには、エンディングノートだけでなく、法律に則った遺言書の作成や専門家(司法書士、行政書士、弁護士など)への相談が必要です。
「Senior Terrace(シニアテラス)」でできること

シニアテラス は、シニアの方々やそのご家族の暮らしをより豊かに、安心して送れるようにサポートするサービスを提供しています。エンディングノートに関する基礎知識から具体的な活用事例まで、さまざまな情報を得ることができます。さらに、終活や老後生活にかかわるお悩みを相談できる専門家やコミュニティにアクセスすることもできるため、「どこから始めたらいいかわからない」という方や「より専門的なアドバイスがほしい」という方は、ぜひ参考にしてみてください。
エンディングノートに関するよくある質問
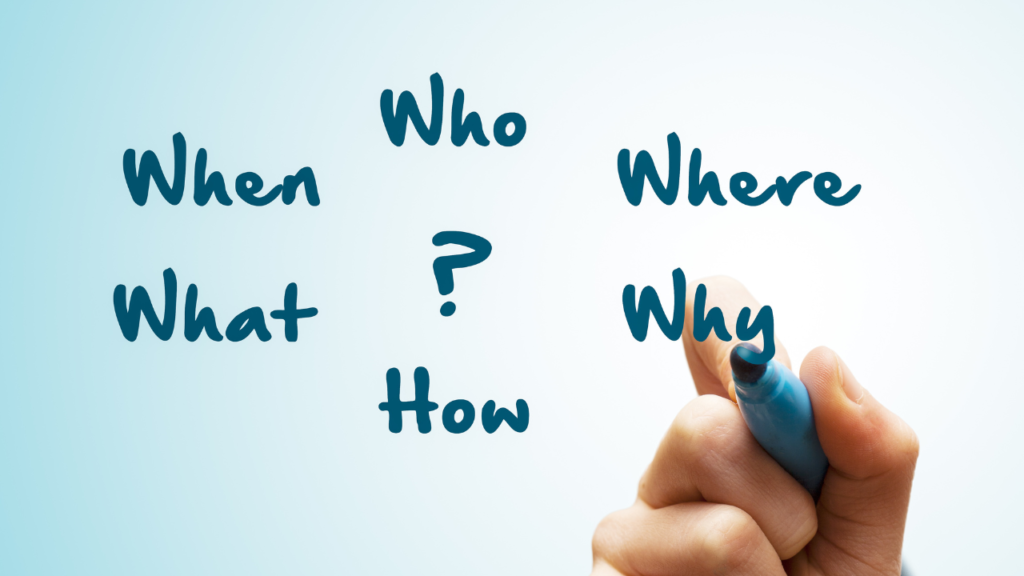
Q1. 若い世代でも作成したほうがいいの?
- はい。エンディングノートはシニアだけのものではありません。若い方でも突然の事故や病気で意思表示ができなくなる可能性はゼロではありません。何らかの持病がある場合や、家族に知られたくない情報がある場合などは、早めに書いておくと安心です。
Q2. エンディングノートと遺言書のどちらを優先すべき?
- 法的な効力が必要な内容(相続や財産分与など)は遺言書が最優先です。一方、「自分の気持ちや希望を伝えたい」という部分はエンディングノートで自由に書き残すのがおすすめです。状況に応じて両方を使い分けると良いでしょう。
Q3. 書いたエンディングノートはどこに保管すればいい?
- 家族が見つけやすく、かつ他人には見つかりにくい場所が理想です。自宅の書斎などのわかりやすい引き出し、もしくは鍵付きの金庫に入れておくケースが多いですが、「どこに保管しているか」を信頼できる人に伝えておくのが何より重要です。
Q4. パソコンやスマホで管理するのは危険?
- デジタルデータは編集や更新が容易な反面、パスワード流出などのリスクもあります。ファイルにパスワードを設定し、さらにバックアップをとっておくなど、セキュリティ対策を十分に行えば便利に使えます。ただし、パソコンやスマホ自体のロックが解除できなくなる可能性もあるため、紙のノートと併用するなど複数の方法を検討するのが無難です。
Q5. エンディングノートは公証役場に預けられる?
- エンディングノートは法的書類ではないため、公証役場での預かりサービスは基本的にありません。公証役場で扱うのは遺言書などの法的効力を持つ文書のみです。ただし、民間のサービスで有料の保管サービスを提供しているところもあるため、必要に応じて利用を検討しましょう。
まとめ
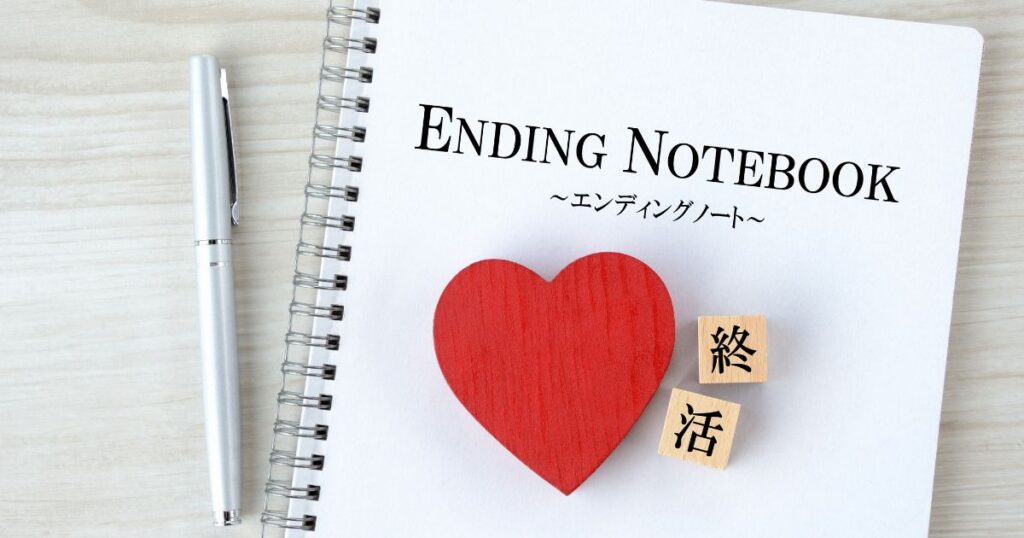
エンディングノートは、自分の最期にまつわる情報や希望を整理し、家族や周囲の人への感謝や伝えたい気持ちをかたちに残せる便利なツールです。遺言書のように法的拘束力はありませんが、その分自由度が高く、書き手の思いを幅広く記録できるメリットがあります。書くことで自分自身の人生を振り返り、これからの生き方について新たな発見を得られるかもしれません。
大切なのは、「書いたら終わりではなく、定期的に見直して更新し、家族や信頼できる人と情報を共有する」 ということです。エンディングノートは、あなたの人生の一部をまとめる貴重な資料になりますが、それ以上に、「あなたがどんな未来を思い描き、どのように大切な人々と向き合いたいか」を考えるきっかけになるはずです。
「Senior Terrace(シニアテラス)」では、エンディングノートに関する基本的な情報だけでなく、終活全般にまつわる専門家への相談窓口や、他のシニア世代の方々との交流の場など、さまざまなサービスを提供しています。今からでも決して遅くはありません。まずは小さな一歩として、“自分のことを整理してみる” ところから始めてみてはいかがでしょうか。
エンディングノートは、あなたやあなたの大切な人たちにとって「安心」と「つながり」を届ける架け橋となるはずです。ぜひこの機会に、エンディングノート作成の第一歩を踏み出してみてください。

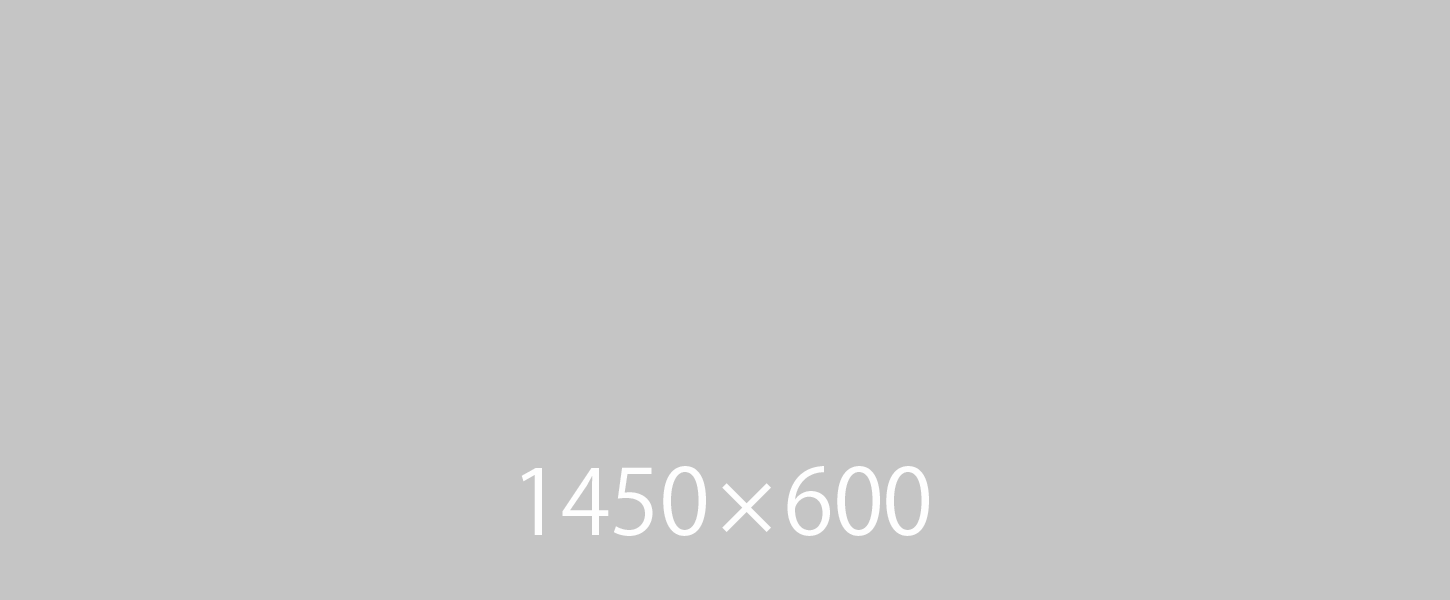
この記事へのコメントはありません。