
デジタル遺品で起きたトラブル事例集とその防止策
1. デジタル遺品トラブルが増加している背景
スマートフォンやクラウド、SNS、ネットバンキングの利用が一般化した現代。人々の生活の大部分がデジタル上に記録されている今、亡くなった方が残した「デジタル遺品」をめぐるトラブルが増えています。これまでは遺品といえばアルバムや手紙、預金通帳でしたが、現在ではアカウント情報、クラウド上のデータ、ネット証券、サブスクリプション契約など、多岐にわたります。
これらは故人の意志が確認できない場合、遺族がアクセスできず、資産や想いが失われるリスクを伴います。実際に起きた事例を通じて、どのような問題が起こるのか、そしてその防止策を学びましょう。
2. よくあるデジタル遺品トラブル事例
事例①:写真や動画のデータが消失
スマホやクラウドに保存されていた家族写真や旅行の動画。パスワードが分からず、ロックが解除できないままスマホが初期化され、貴重な思い出が失われたというケース。GoogleフォトやiCloudのバックアップも、ログイン情報がなければアクセスは困難です。
事例②:ネットバンキングや証券口座の資産にアクセスできない
亡くなった親がネット銀行やネット証券を利用していたが、口座がどこにあるのか分からず、多額の資産が長期間眠ったまま。郵送書類もペーパーレスだったため、気づくのが遅れたという事例もあります。
事例③:有料サブスクリプションが解約できない
Netflix、Amazon Prime、スマホゲーム課金など、自動引き落としされるサービスが多数あり、本人の死後も数か月にわたって課金が続いた例。気づいた時には数万円が無駄になっていたという声も。
事例④:SNSアカウントが乗っ取られる
放置されたFacebookやInstagramアカウントが悪意のある第三者に乗っ取られ、詐欺まがいの投稿をされてしまった事例。遺族にとっては精神的なダメージも大きいものです。
事例⑤:仮想通貨のウォレット情報が分からない
故人が生前に仮想通貨で資産運用をしていたが、ウォレットのID・パスワードが分からず、数十万円以上が取り出せないままとなった例。パスフレーズを知らなければ回復は不可能です。
3. トラブルが起きる主な原因
- アカウント情報やパスワードが共有されていない
- クラウドやネットバンキングなどが「見えない資産」になっている
- デジタル遺品の整理が生前に意識されていない
- 書面の遺言では触れられていないデジタル資産が多い
- 死後、家族が何に手を付けてよいか分からない
4. トラブルを防ぐために今できる5つの対策
① エンディングノートにアカウント情報を記載
SNSやクラウド、ネット証券など、使っているサービスを一覧にまとめておくことで、遺族が早期に対応できます。パスワードはメモや管理アプリの場所だけ記載しても良いでしょう。
② パスワード管理アプリの活用
1PasswordやLastPassなどのツールに情報を集約し、信頼できる家族に引き継ぐ方法。生前に共有用のログイン情報を残すことで、対応が可能になります。
③ サブスクリプションの定期的な見直し
契約中のサブスクを定期的に確認し、不要なサービスは解約。重要な契約だけを明示しておくことが、死後の混乱防止になります。
④ クラウドデータはバックアップしておく
GoogleフォトやiCloudに保存されているデータは、外付けHDDやUSBなどにバックアップを取り、物理的な形で残しておくことも検討を。
⑤ 死後事務委任契約を活用する
信頼できる第三者に、死後のアカウント削除やサブスク解約などを委任する契約。専門家や法人と契約することで、責任を持って処理してもらえます。
5. トラブルを避け、安心してデジタル資産を引き継ぐには
デジタル遺品は、放っておけば大切な情報や思い出が失われるだけでなく、経済的・精神的なトラブルに発展することもあります。自分の死後、家族が困らないよう、今から準備することが何よりの思いやりです。
まずは身近なところから、「何を使っているか」「どこに情報があるか」を書き出してみましょう。それが大切な人を守る第一歩になります。
シニアテラスのデジタル遺品トラブル防止サポート
シニアテラスでは、デジタル遺品に関するあらゆるお悩みに対応しております。
✅ アカウント情報の整理・一覧化のサポート ✅ 専門家によるデジタル遺品管理アドバイス ✅ 死後事務委任契約・エンディングノート活用支援
トラブルになる前に、ぜひ シニアテラス にご相談ください。

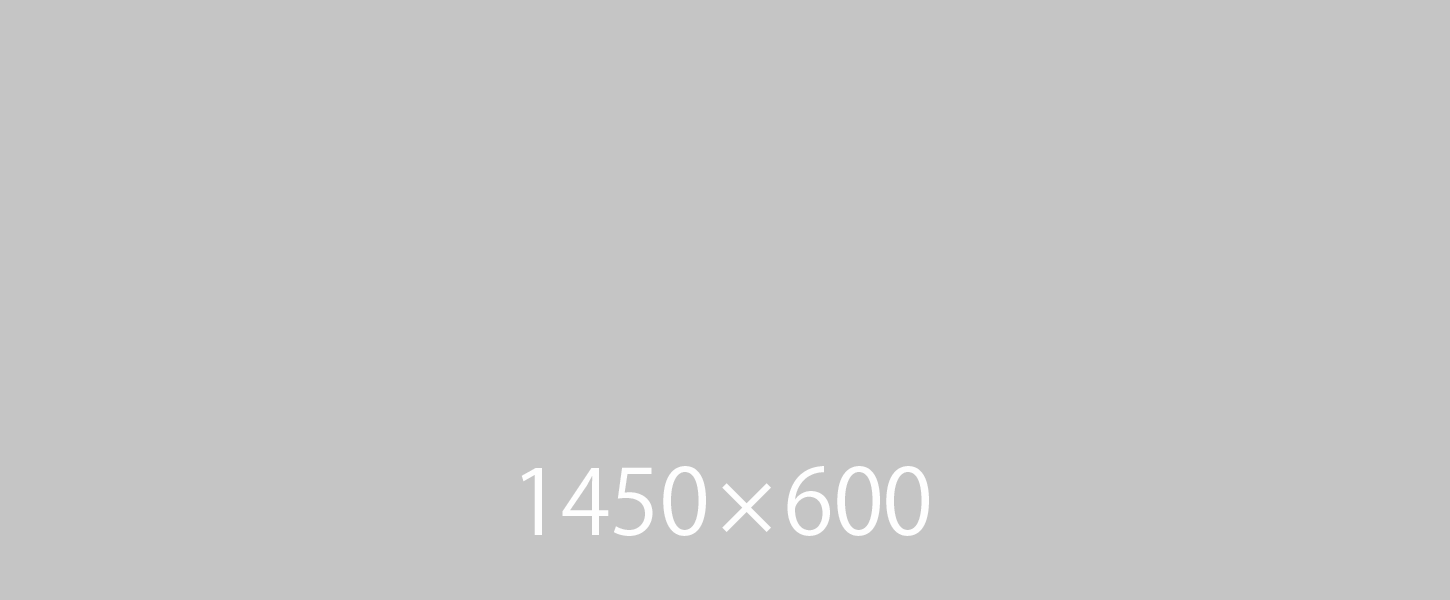





この記事へのコメントはありません。